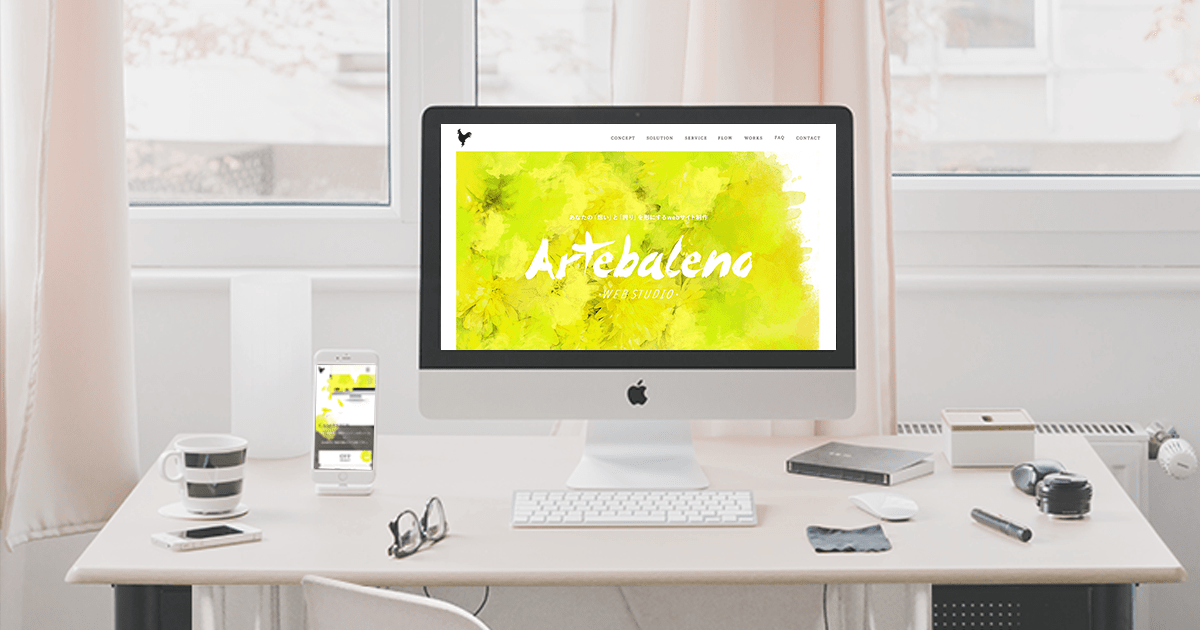ホームページの管理を
誰に頼むか
CHOOSE THE RELIABLE PARTNER
ホームページにメンテナンスが必要な理由と、放置する危険性は別稿で書きましたが、ではホームページ公開後、有益なメンテナンスやサポートを受けるにはどうすればよいか。制作元へ保守管理を依頼するメリットなどについて本稿では解説していきます。
制作後の契約関係
最初に申し上げておくと、制作会社としても、作ったホームページは公開後も末永くお手入れさせていただきたいものです。
更新や集客・広告については相談してもらいたいし、こちらからもタイミングよく提案したい。なにかあったときにすぐに相談できる相手でありたい。
ホームページを通して、お客様と永い信頼関係を築けるのは、制作会社としての本懐ではあります。
……とはいえ、とはいえですよ。
ホームページを公開したら契約関係はなくなる
ホームページ制作の大前提として
制作したホームページの公開が終われば、制作会社の仕事は(一旦)終了です。
一般に、制作やリニューアルのお見積りは、制作完了までの対応費用で、その後の更新・相談については含まれない=別途契約が必要なケースがほとんどだと思います。
もちろん「永久保証」を謳う制作会社もあるので一概には言えませんが、それはその制作会社のビジネス戦略上の特例と考えるべきです。
一方で、公開後の修正や相談対応について費用の相談がうまくいかないことは多くのWebディレクターの悩みの種で、その理由が、お客様と制作会社の間でここの認識がズレているせいなのかな、と。
家に例えると
ホームページの制作は、新築の家を大工さんに依頼するのと同じようなものです。
家の設計図から家の完成・引き渡しまでは、設計図の修正やリクエストに応じた提案は「家を新築する」という当初の契約に入っていますが、引き渡し後はどうでしょう?
- 定期的に家の見回りして、補修箇所の点検をすべきですか?
- 壁の塗装や雨漏りの修繕を、永久無料ですべきですか?
- 万一のときのために合鍵を保管しておくべきですか?
多くの場合「NO」で、やはり家のメンテナンスやセキュリティについては、別途依頼をしますよね。
もちろん「うちの大工さんは、定期的に見に来てくれるよ」という場合もあると思いますが、それも大工さんのご厚意であったり、(ビジネス的には)メンテナンスの依頼につなげる意図があるわけで……。
お家のことでお困りごとないですか~?
そうそう、壁の塗装が古くなっているから塗り直してほしいかも
では、お見積りこのくらいで……。
え? お金とるんですか!?
と、タダでやってもらえると思うのは、やはり大工さんのご厚意に甘えすぎな感じを受けますよね。
それと同様に
お金とるなら自分でやるんで、やり方教えてください。
というのもやはり、マナーが悪いと申しますか……長年習熟を積んで技術を手にした大工さんにとっては、軽々しく言われるのは気持ちの良い話ではない、ということは想像に難くないと思います。
それがホームページ制作になると状況が変わり、修正費をお支払いいただけなかったり、やり方を教えてくれ、と平気で言われたりするのはなぜなのか……。おっと、つい愚痴が……。
悪気はないとは思うのですが、やはり「ホームページ制作の契約は、納品完了で終了する」という認識が、社会全体として浸透していないことが原因のように感じています。
弊社では……
そのような経緯もあり、弊社では、納品(公開)後は、各種アクセス権限を返却し、制作契約は終了/以降の保守管理は別途契約という基本方針をとっています。
これは決して「公開後は無関係です」と言いたいわけではなく、冒頭で述べたように、本当はメンテナンスも弊社で引き続き対応させてもらいたいんです。
しかしながら納品した時点で、法的にはなんらの権利義務関係もなくなるということを明示することは必要だと思っており、そのため、管理用のデータをお返しするということで区切りを明確にすることにしました。
そしてその上で「メンテナンスも御社に頼みたい」と、意思をもって弊社を選択してもらうことが、双方の信頼関係を強固にし、ネット集客という長い道のりを歩むパートナーとなる一歩となると、弊社では考えています。
メンテナンスを誰に頼むか
「メンテナンスをしない」という選択肢はないので、メンテナンスについては下記の選択肢のいずれか、ということになります。
- ホームページを制作した会社に続投してもらう
- 他の制作会社・事業者に依頼する
- 自社内で行う
弊社で制作したサイトについては、公開(=納品)後に他社へ移管してもらっても問題ありません。納品(正確には制作費のご入金完了時)時に、ホームページを管理するためのサーバー情報やGoogleアカウント情報は、下記のような資料にまとめ、すべてお引き渡ししています。
この情報があれば、弊社でなくてもホームページ制作スキルがある会社・事業者なら、ホームページの更新や改修を行うことは可能です。ただし……。
「教えてほしい」はご法度
ときどき移管後に
- 画像を追加したいので、やり方を教えてほしい
- 自分で修正したら表示がおかしくなったので直してほしい
- 後任の制作会社が作業の仕方がわからないらしいので手伝ってやって
といった連絡をいただくことがあるのですが……。
これ、家と大工さんの例にすると、ですよ。
- 飾り棚をDIYしたいので、作り方を教えてほしい
- 自分で壁を塗ったら汚くなったので、きれいに塗り直してほしい
- 後任のメンテナンス会社に修繕技術がないので手伝ってほしい
できないなら素直に頼んでって最初から言ってるでしょーーー!
と思わず叫んでしまいたくなる気持ち、おわかりいただけますやろか……。
当初の契約は納品で完了している以上、その後、DIYしてもらっても、他社に管理や改築を依頼してもらっても、弊社としては構わないんです。
でも、失敗したらそれをやらかした業者の責任でしょという話で。
その失敗の尻拭いを当然のように制作元に持ち込まれると、ちょっと「んん?」と思ってしまったりはします。
あ! 当然ながら、ちゃんと修正対応のご依頼と対応費をいただけるならウェルカムです……!
移管先のスキルに注意
特にホームページ制作の場合、その仕組み自体は世界共通で(巧拙はありますが)、修正や改修方法が「わからない」ということはまずないですし(システムが絡む場合はこの限りではありませんが)、何かを請け負った以上、他社へ外注する検討も含めて「なんとかする」のがまっとうな制作会社の姿勢だと思うんですよね。そのはずなのですが……
- コンテンツを追加したら表示が崩れた
- PhotoshopやIllustratorを持っていない
- どんなバナーにしたらいいかわからない
- 広告タグを追加するってどういう意味
もう君、「Web制作」の看板捨てたまえよ!
というレベルの(これは同業者向けの笑いどころですが)、なかなかパンチの効いたことを制作元に臆面もなく訊いてくる方も実際いらっしゃるわけです……。
保守管理契約をつけない/ホームページを移管する、ということは制作元のサポートは受けられなくなるということです。
必ずしも制作元に継続依頼しなければならない、ということはありません。ただし保守管理もまた、安さだけではなく、信頼できる技術と知識を持った会社/事業者を選ぶ必要はあります。
作る以上の修復費がかかることも
というのも、たとえばいつもと違う美容室にいって、ひどい髪形にされてしまったとしましょう。で、いつもの美容室に直してもらえることになったとしても、切られすぎていたらエクステをしたり、髪を施術ミスでボロボロにされてしまったら補修やトリートメントが必要になるなど、本来ならば必要なかった修復費がかえって高くついた……。そんな経験をされた方ももしかするといるかもしれません。
ホームページも同様で、あまり技術・知識のない方に管理を依頼をしてしまい、なかなかボロボロな状態で、困り果てて元制作者に帰ってこられるケースもあります。
もちろん技術的なことであれば元に戻すことは可能ですが(費用は掛かりますが)、たとえば安易なマーケティングで会社の信用やブランド自体が毀損してしまった場合、失われたものを取り戻すのは絶望的になります。
だからこそ、ホームページの移管先は慎重に、信頼できる会社/事業者を選んでもらいたいと思うわけです。
継続で依頼するメリット
ホームページの移管を検討する理由はいろいろあると思いますが、ホームページ完成時、その仕上がりに満足されたら、基本的に管理も継続して制作を担当した制作会社に依頼することがおススメです。
対応がスムーズ
ホームページの内容や仕様はもちろん、制作時にどういった意図や議論があったかも把握しているので、細かい情報共有なしに、的確かつ円滑に対応してもらえるという利点があります。
軸がぶれない
(弊社の場合)制作の前提として、商品コンセプトやターゲット像、マーケティング戦略なども共有するため、ホームページ公開後の運用・改修についても、一貫した軸で展開することが可能です。特に中長期での積み上げが必要なブランディングで、ビジネスモデルを把握している制作会社とのスクラムは力を発揮します。
「車輪の再発明」を防げる
特に保守管理を自社で内製化される場合に多いのですが、何かやりたいことがあったときに、制作会社にはすでにノウハウが蓄積されていることが多くあります。
もちろん御社内で試行錯誤されながら正解にたどり着くことを否定はしません。しかし、ネット集客は情報戦です。既に確立されている手法について手探りで検証している間に、ライバルたちはどんどん先へ行っています。
知見のある制作会社を専門の相談先として持っておくことで、こうした「車輪の再発明」を防ぎ、有利なPDCAを回すことが可能になります。
スキルは保証されている
制作会社の技術・知識は正直なところ玉石混交で、ご発注者側でその見極めをするのは少し難しいかもしれません。
その点、満足ゆくホームページを制作した会社/事業主は、ホームページをゼロから新築できるスキルを持っていることは確かであり、少なくとも管理・修繕ができないということはないでしょう。
制作会社とは流派や相性もありますので一概には言えませんが、特に制作元の対応や関係性に不都合がなければ、管理も続投してもらうのが安心だと思います。
まとめ
多くの制作会社では、その制作物は自分たちにとっても思い入れがあり、できれば末永く守ってゆきたいと思っています。それゆえ、納品後の保守管理も継続してご依頼いただけることは、とても嬉しく、また名誉に思うことでもあります。
一方で制作に関する契約は、納品で終了するという前提もまた、弊社だけではなく多くの制作会社の暗黙としているところだと思います。
しかしご発注者様とこの前提を共有できていないことで起こる摩擦も多く、そのため今回改めて記事として書かせていただきました。
ホームページは作って終わり、ではなく、その後の更新・運営・改修等も継続的に必要であり、そのためには信頼できる制作会社とのパートナーシップが不可欠です。
この記事が、巡り会った制作会社と、永く好い関係を築く一助となれば幸いです。
弊社での対応
弊社では、契約範囲の明確化と情報管理の観点から、納品(公開)をもって業務完了とし、保守管理は別途の契約をお願いしています。(制作後の流れ/ホームページの保守管理)
スピーディーな対応をさせていただくための年間契約や、ご相談を含めた顧問契約なども設定がございますので、弊社で制作をお考えの際、公開後の体制・ご予算についての参考になれば幸いです。